受刑者が考察・3つの事件組織的隠蔽
2024年6月に相次いで発覚した、3つの事件について、警察や検察と対峙してきた受刑者ならではの視点で考察してみたい。
まず「鹿児島県警での不祥事を本部長が隠蔽した疑惑」だが、鹿児島県警の元生活安全部長が内部文書をライターに漏えいした国家公務員(守秘義務)違反で逮捕・起訴され、裁判所の勾留質問で、昨年12月県警枕崎職員による盗撮事件を県警本部長が「泳がせよう」などと操作せず不祥事を隠蔽しようとした事が許せなかったとの動機を述べている。
本部長は記者会見で、県警主席警察官(当時)からの報告で、証拠に乏しく、捜査を尽くすよう指示したとし、元生安部長が本部長に報告や捜査指揮伺いに来た事実は一切ないと隠蔽を否定した。
だが盗撮事件で証拠映像がない事自体あり得ない(余罪の映像も残っているはず)。更に証拠に乏しいという発言が証拠があった事を物語っている。
また、現職警察官が交番の巡回連絡簿を悪用しストーカーした事件は、被害者が事件化を望まず本部長指揮により捜査を終結したとされるが、そもそも性犯罪が今は親告罪ではないのだから詭弁でしかない。
4月に県警曾於署巡査長による別の情報漏えい事件の関係先として、ニュースサイト運営会社の代表取締役男性宅を捜索したが、このニュースサイトが県警の一連の不祥事を報じていた事から男性は「報道機関への脅し」だと反発している。
ストーカー事件の内部文書には被害女性の個人名や年齢が記載された状態でライターに漏えいしており、本部長は「公益通報には当たらない」との見解を示した。しかし、ライターに漏らした行為を公益通報とするには無理があるとしても、ライターの公表後に逮捕した本部長の対応は隠蔽を否定しても無理がある。
ニュースサイト運営会社代表宅の捜索にも問題があるし、本部長が隠蔽をしたか否か証拠がない生安部長とのやり取りを否定しても無理がある。
おうした、「泳がせよう」などとする手法は良くある事で、現在警察庁の特別監察を行っているが、隠蔽の有無に関らず、疑惑がある当事者の本部長はすぐにでも交替させるべきだろう。
次が「沖縄で米兵による性犯罪事件」だが、捜査当局と政府の間で情報が共有されていたのに、昨年12月と今年5月の事件を報道で把握した県側が政府に問い合わせるまで伝達されていなかった政府の対応に沖縄県で反発が強まっている。
1997年の日米合同委員会で外務省や沖縄労働局が米側から事件・事故の連絡を受け、県に伝えると定められた。
知事は「日米間で合意した通報手続きに基づき、情報提供の徹底を求める」と政府を批判した。
28日に上川外相は記者会見で速やかに政府が県に伝えなかった理由を「捜査当局は関係者のプライバシーや捜査、公判への影響の有無などを判断したうえで、公表するか否か判断した。外務省としてもその判断を踏まえて対応した」と説明し、県警と地検は性犯罪の特性から被害者のプライバシー保護を最優先に考慮し、伝達しなかったと明らかにしている。
だが、被害者のプライバシー保護は被害者の個人情報や事件の詳細など、被害者の特定に繋がる情報を秘匿する事で守られるし、犯人の個人情報や容疑事実までも公表しないという捜査当局や政府の説明は詭弁である。
これは「政治とカネ」で揺れ、低支持率に喘ぐ岸田政権が報道で発覚するまで県に伝えず隠蔽したのだ。
もし、沖縄県議会選挙の前に発覚していたら、自民・公明など与党が負けていたはずで、沖縄県民を欺いたのだ。
昨年12月の事件では3月に駐日米国大使に外務省が再発防止を求めたにも関らず、5月に再び事件が起きてもなお、6月下旬の報道まで県側に伝達していなかった政府の対応には沖縄県民を軽視している事を物語っている。
捜査当局も政府も、被害者のプライバシー保護を理由にすれば非公表でも問題ないとする方針は、報道で知る権利を侵害するものだと、報道機関側も問題視すべきだろう。一般人の性犯罪は報道し、米軍や法曹界関係者の事件を報道しない事に正当性はない。
昨年の12月の事件後、速やかに県側に伝達していれば、5月の事件を防げた可能性もあり、政府や捜査当局の失態であり、明らかに隠蔽だといえる。(その後、3件発覚)
最後は「元大阪地検トップによる準強制性交事件」である。
大阪地検のトップだった検事正が5年前の在任中に、官舎で部下の女性を酒を飲んで抵抗できない状態で性的暴行を加えた事件で、今頃になって大阪高検が逮捕した前代未聞の事件である。
大阪高検は被害者のプライバシー保護を理由に、容疑者名だけ公表しただけで記者会見すらしなかった。
大阪高検のこうした姿勢に批判が噴出し、起訴後に方針を変えマスコミを集めて説明し、隠蔽を否定したが、5年前の事件を今頃になって逮捕した事が隠蔽と思われてもやむをえないだろう。
5年前と言えば、森友学園による国有地売却に絡む一連の事件の指揮をし、財務省理財局長の佐川氏を不起訴としたのがこの検事正である。
更に不可解なのが、この検事正が、定年退職を前にして検察を退官している不合理な点を考えると、この事件を隠蔽するかわりに退官させたのではないか。
しかも、この時期は、黒川元東京高検検事長の定年を延長した閣議決定により、官邸に近いと目された黒川氏を検事総長にする為に官邸主導で動いた時期である。大阪高検は5年前の退官は本人の希望によるものとし、今年2月に女性が検察幹部に相談し、処罰を望んだとしているが、疑しい。
警察・検察は身内に甘く、組織のメンツを重んじる。法の行使は大変重く、1度下した決定や判決の非を認める事が公権力としての根幹が崩れるのを恐れる。だからこれまでの冤罪事件や袴田さんの事件でも非を認めない。不動産会社(プレサンスコーポレーション)や軍事転用可能な機械を輸出しようとした事件など検察は非を認めない。
旧優生保護法など、国も最高裁で判決が確定するまで認めない姿勢といい、国も司法も過ちだったら素直に認めるべきではないか。これら3つの事件では被害者のプライバシーを守る事は必要だとしても、それを配慮した上で公表し、国民の報道を知る権利を侵害する事が無いよう、マスコミ・報道機関は説明責任を果たすよう求めるべきだ。また第三者機関による調査で真相究明する事も必要だろう。
2024/7/3
A49さんの過去の投稿
※上記ボタンをクリックすると決済ページへ移動します。決済方法に関してはこちらをご確認ください。
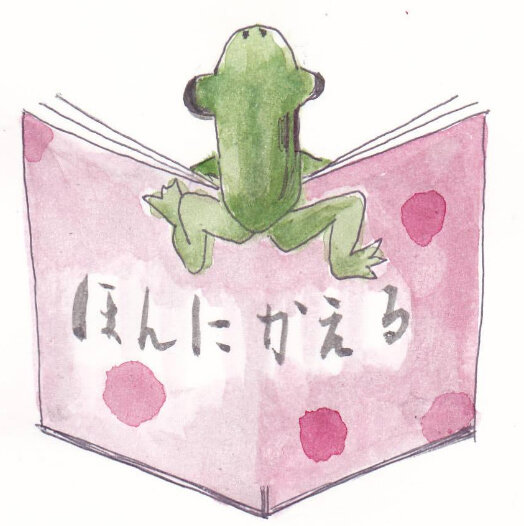


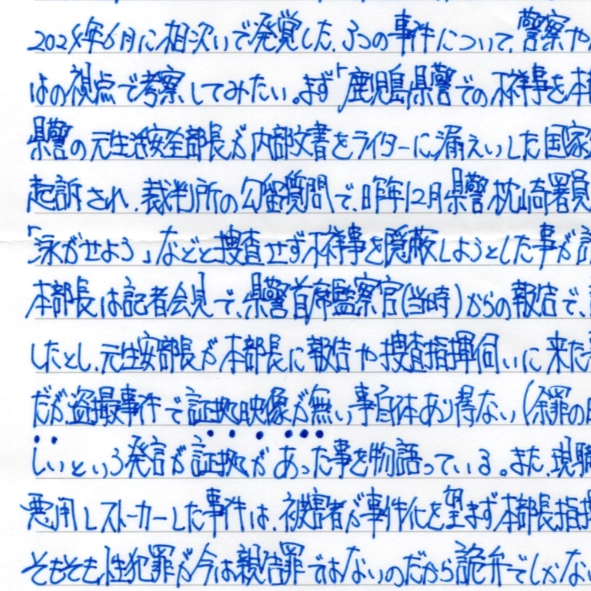

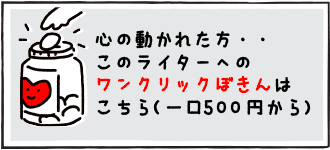

令和5年の「犯罪白書」の内容から、刑務所の今を書いてみたい。全国の刑事施設は刑務所59庁・少年刑務所7庁・拘置所8庁、支所が刑務支所8庁・拘置支所94庁あるが、令和4年末現在、収容定員8万5680人(・・