無期刑18年目、償えずに終わる
刑は罪への罰であって、償いではない。
だから、刑期を終えて刑務所を後にしたからといって、それで全てが許されて終わったわけではない。
刑務所を出てからが、本当の償いの始まりなのだ。
このような言葉を、これまで何度か聞いてきた。
私自身が罪を犯す前にも、犯してからも。
私も刑務所で刑に服しながら、同じように考えていた。
罰とは別に、償いをしなければならないと。
でなければ、今こうして生かされている意味がないと。
でも、ある時、はたと思った。
私が被害者の命を奪ってから20年近くが経つのに、未だなにひとつ償えていないばかりか、場合によっては一生償えずに終わるのではないか?
私は今、無期懲役刑という罰を受けているだけで、これは償いではない。
そして、読んで字のごとく刑期は無期限なので終わりはない。
終わらないから償いに入れない。
法で裁かれたのに、その法によって償いをさせてもらえないままで終わってしまうかもしれない。
少し前に、同じ工場に勤めていた無期刑の高齢の人が、体調を崩して工場からいなくなってしまった。
いなくなった、ということは、そういうことなのだろう。
刑務所なので、他の受刑者のその後を教えてもらえることはまずない。
出所した人なら風聞を耳にすることは、まだなくはない。
でも、大病した人が工場を離れてそれっきり、ということはままある。
病気が治れば戻ってくるので分かるけど、そうでない場合は、となる。
これが決して他人事ではないと思ったとき、死への恐怖はまったく湧かないが、償えないまま終わるということに恐れを覚えた。
私は仏教徒、それも浄土宗徒なので生前の罪が死後のそれに関わるということはない。
なので、教義的に罪を償うべし、というのではない。
阿弥陀如来にお救い頂けるから何をやってもいいという訳ではないし、お救いを求める身としてそれに報いれる行いをせねばと心掛けているので、信仰心とまったくの無関係というのでもないけど。
自分の犯した罪を考え、それによって苦しめてしまった、今もなお苦しみの中にいらっしゃるであろう御遺族や、私の親姉兄を思うと、罪の重過ぎる重さに、償わないという選択肢はないと思い至っている。
が、その発露が難しい。
中嶋博行著「罪と罰、だが償いはどこに?」新潮社、1500円(税別)という本を読んだ。
この本は、弁護士でもあり刑事事件を担当したこともある著者が、自身の経験と、日本とアメリカで実際に起きた事件や、司法、刑務所の制度から、被害者救済と無犯罪社会の実現に向けた提言をしている。
2004年の発行で、私が事件を起こす前にはすでにあった本だ。
この本に限ったことではないけど、事件を起こす前に知っておけば、もっと世の中に目を向けていれば、と思い、我が身を引き裂きたくなることがままある。
本の中で著者は犯罪者の改善更生がいかに難しく、刑務所による更生プログラムが無力であることを実例を挙げて説いている。また、司法制度の中で被害者がどれほど無礙に扱われてきたかも教えてくれている。
この中で語られている被害者の嘆きや悲しみが、私が起こした事件の御遺族の思いでもあると思うと、申し訳なさに頭が下がる。
本文中に、資本主義の世のなかでは、あらゆる被害が金銭的損害として評価される、とある。
確かに、奪ってしまった命をお返しできない以上、何らかのかたちにしいて償おうとするならお金を払う以外にないのか。
でも、償いとお金が私の中で上手く繋がらない。
即物的なものでいいのか、と考えてしまう。
だからといって、他に何があると訊かれても答えようがないのだけど。
償いとは何か?という本質的なところが分からなくなってしまったので、広辞苑を引いてみた。
償う・・・財物を出し、あるいは労働して、恩恵に報い、また責任や罪過をまぬがれる。
うめあわせる。賠償する。
財物を出し、まぬがれる?なんだか腑に落ちないな。
手元に小学館の新選国語辞典もあったので、そちらも引いてみた。
償う・・・➀かねや品物で、損失をうめあわせる。
②かねや品物・労役などで、罪や責任をうめあわせる。
まだ、まぬがれる、よりも、うめあわせる、の方が語感的にフィットする気がするけど、それでも前提としていたものが崩れていく音が聴こえるのは気のせいだろうか。
文面をそのまま読めば、懲役刑をうけて受刑生活を全うすれば、それも償いとなるように思える。
罪と罰、償いはどこに?
アンサー、罰に含まれてます。
いや、待て。これで納得してしまってはダメだ。本の中でも著者は、犯罪被害者が賠償請求の満額を手にしたという噺は一度も聞いたことがない、と言っている。刑に服すのも償いの
ひとつだ、で止まってしまうと、私もそうなってしまうかもしれない。
言葉通りの意味だとしたときに、何が腑に落ちないのだろう。
賠償の支払いも刑に服すのも、そこからは気持ちが見えてこないのか。
支払いは金銭だけのやり取りだし、刑に至っては否応のない強制だ。
これだけでは私が罪を悔いて反省し、謝罪の念とともに更生すべく励んでいることが御遺族には見えないか。
この思いをかたちにして伝えることが必要なのか。
でも、謝罪の思いを手紙にしたためたとして、本当に出していいのかとも思う。
逆に、御遺族のお心をお騒がせしてしまわないだろうか。
事件から20年近くが経つ。
時が経ったからといって御遺族のお心が晴れることはないだろう。
それでもこれまでの日々において何かと一日一日と日常の生活を取り戻すべく努力してこられたであろう御遺族の静謐を乱してしまうかもしれない。
それが、恐ろしい。
私が起こした事件によって、御遺族にはこれ以上ない苦しみを与えてしまった。
なのに、私の何らかの行為がさらに御遺族を苦しめてしまうかもしれない。
それが申し訳なくて、何も行動に移せない。
それに、心からの謝罪をしても、奪ってしまった命をお返しすることが出来るわけではない。
謝罪し、刑を勤め上げ、賠償を全額支払ったからといって、それが御遺族にとって一体何になるというのだろう。
なにがしかの慰めになるだろうか。
償いをしたという私の自己満足でしかないのではないだろうか。
罪と向き合い、己の仕出かしたことの重大さを真に理解して心から更生した上で、許されることなくこの生を終わる。
全てを奪ってしまった被害者にいくらかでも報いるには、私の思いが達っせられることなく、あるいは達っする見込みが見えたところで断ち切られるようにして終わる。
それが私に相応しい終わり方なのではないだろうか。
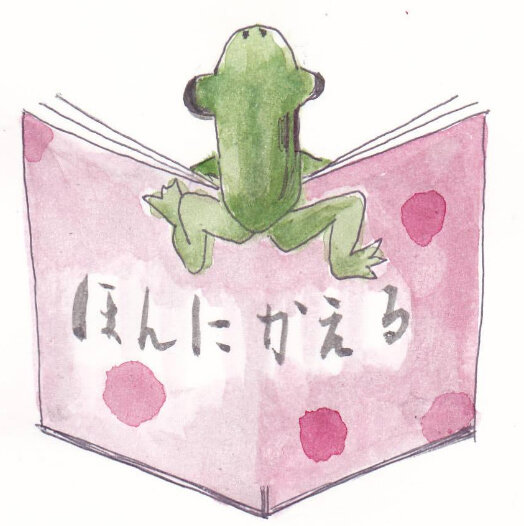




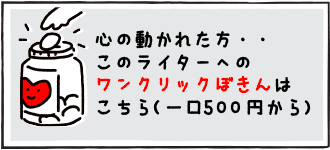

日々、額に汗して刑務作業に励んでいる我々受刑者ですが、我々にとっての「一日」と世の中の人にとっての「一日」では長さが違います。 刑務官の日中の勤務時間の中で、受刑者を部屋から出して作業をさせて飯を食わ・・